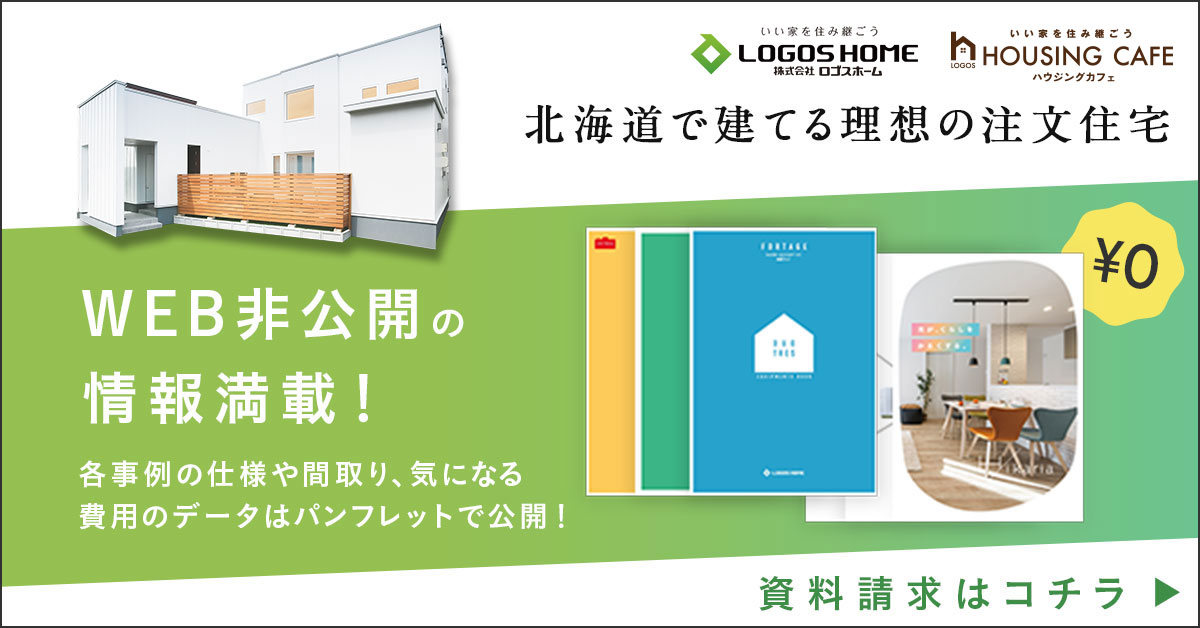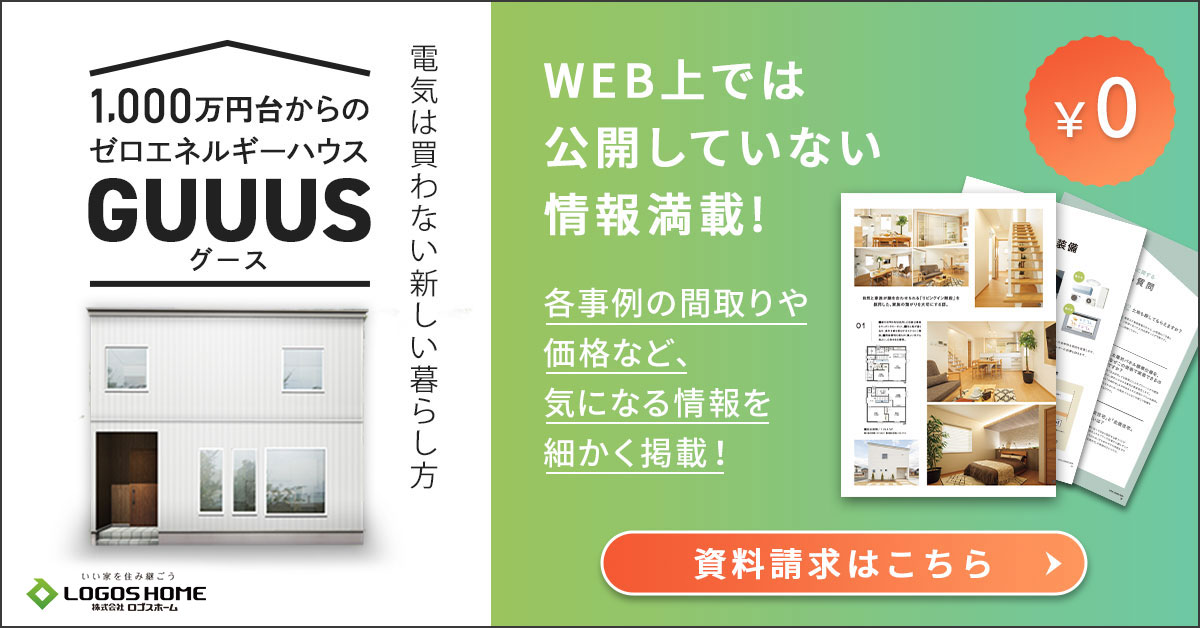この記事の目次
北海道の厳しい寒さから身を守るためには、住宅の断熱性能が非常に重要です。これから新築する際は、どれほどの断熱レベルが必要なのか把握しておくと安心できるでしょう。
本記事では、北海道の気候に適した断熱等級や、外壁・屋根・床など部位別の断熱方法、そして断熱材の種類について詳しく解説します。北海道で家を建てるなら、断熱は必須。適切な断熱レベルで、快適な住まいを実現しましょう。
最低ラインの断熱等級は?
断熱等級の最低ラインは、等級4または等級5に相当します。
これまで家を建てる際に、断熱性能の基準を選ぶことは、地震の強さに対応するための「耐震基準」とは違い、必ずしも義務ではありませんでした。しかし、2022年4月から新しい断熱性能の基準として等級5ができたことで、それまで最高レベルだった等級4が、最低限必要なレベルに変わります。
そして、2025年度からはすべての新築住宅で等級4以上の断熱性能が法律で義務付けられます。言い換えれば、等級4よりも低い断熱性能の家を建てられなくなるのです。
この等級4は、1999年から使われていた基準で、2022年3月までは最も高いレベルの断熱性能とされていました。多くの住宅会社が“高断熱”と呼ぶ場合は、この等級4を指していることが多いです。
一方、近い将来で断熱性能の最低基準は大きく変化します。というのも、2030年までには等級5以上が義務となり、等級4以下がなくなる予定だからです。
つまり、これから家を建てる際には、最低でも断熱等級4または等級5の家を選ばなくてはなりません。
断熱等級の違い
断熱等級は住宅の断熱性能を表す指標で、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示しています。ここで、2025年度以降の断熱等級とその違いについてまとめてみました。
| 断熱等級 | 特徴 |
| 等級4 | 省エネ基準。 ※2025年度から ※2030年までに廃止予定 |
| 等級5 | ZEH基準。 ※2030年までに適合義務化予定 |
| 等級6 | ZEHを超えるHEAT20 G2レベル ※当面の目標数値 |
| 等級7 | ZEHを超えるHEAT20 G3レベル ※2050年までの長期目標 |
※2025年度より等級3以下は廃止
最低基準となる等級4は、壁や天井に加え、開口部に複層ガラスを使用するなどの規定が追加されたものです。
そして等級5は、等級4よりもさらに水準の高いZEH基準の断熱性能を持つ住宅のことです。たとえば、天井や壁に使う断熱材の厚みが、等級4の住宅と比べて約1.2倍も厚くなっています。断熱材が厚いほど、外からの熱が家の中に入り込みにくく、冷暖房の効率がアップします。
等級5以上に求められる“ZEH基準”とは、年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指した基準であり、北海道などの寒冷地では太陽光発電が不要でもZEH認定を受けることが可能です。経済産業省においても“2030年時点でZEHの住宅を標準的な住宅とする”という目標を掲げています。
等級6なら、一次エネルギー消費量の削減率が約30%可能な状態を指します。等級7なら、一次エネルギー消費量の削減率が約40%可能な状態であり、ここまで来ると暖房がなくても快適に過ごせるレベルです。
▼ZEHについては、こちらの記事も参考にしてみてください。
等級6、7に関してはZEHの性能基準を上回るHEAT20という基準が当てはまります。HEAT20については、次の章でご紹介しましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
北海道で選ぶべき断熱レベルはどれくらい?
北海道で家を建てる、また断熱リフォームを行う際は、断熱等級6または7が必要です。等級6または7の基準であるHEAT20は「一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」によって定められた、“より快適で、エネルギー効率の良い住宅を実現するために、具体的な数値目標”をいいます。
HEAT20のG2、G3それぞれの断熱性能について、北海道の省エネ基準地域区分を基準に以下の表にまとめました。
| 1・2地域 (北海道ほぼ全域) |
3地域 (函館市・室蘭市など北海道の東北寄りの地域) |
|||||
| グレード | 冬の室内適度環境 | 体感温度が15%未満となる割合 | 暖房負荷削減率 | 冬の室内適度環境 | 体感温度が15%未満となる割合 | 暖房負荷削減率 |
| HEAT20 G1 | おおむね13℃を下回らない | 3%程度 | 約20%削減 | おおむね10℃を下回らない | 15%程度 | 約30%削減 |
| HEAT20 G2 ※断熱等級6相当 |
おおむね15℃を下回らない | 2%程度 | 約30%削減 | おおむね13℃を下回らない | 8%程度 | 約40%削減 |
| HEAT20 G3 ※断熱等級7相当 |
おおむね16℃を下回らない | 2%未満 | 約50%削減 | おおむね15℃を下回らない | 2%未満 | 約60%削減 |
最高グレードの断熱性能を求めるなら等級7となりますが、
・建築コストもそれほど高くない
・光熱費を安く抑えられる
・どのような冷暖房設備でも一定の効果が得られる
以上を考えると、現時点で十分に実現できる等級6がベストと言えるでしょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
断熱方法の主な種類
住まいの断熱方法には、充填断熱工法や外張り断熱工法などのさまざまな種類があります。ここで、断熱方法の種類を7つご紹介しましょう。
1:充填断熱(内断熱)工法
充填断熱とは、建物の構造体(柱や梁など)の間や壁の中に断熱材を充填する工法です。一般的な断熱方法の一つで、施工が比較的簡単で費用も抑えられるのが特徴です。
メリットは、施工が簡単で費用が抑えられるという点、そしてデザインの自由度が高い点にあります。その反面、断熱性能が外断熱に比べて劣ったり、結露のリスクが高かったり、経年劣化によって断熱性能の低下したりと懸念点も多いです。
コスパ重視派には充填断熱工法が適していますが、デメリットを踏まえ、外張り断熱工法との比較をおすすめします。
2:外張り断熱(外断熱)工法
外張り断熱とは、建物の外側に断熱材を直接貼り付けて断熱を行う工法です。建物を外側から覆うため、まるでコップに氷水をかけたように外気の影響を遮断し、室内の温度を安定させます。
断熱性が高く結露防止効果も期待できるため、快適な室内環境を実現できるのがメリットです。その反面、施工費が高くデザインの自由度が低い、さらに工期が長いというデメリットもあります。
高い断熱性能で長期的に快適な住まいにしたい、そんな人には外張り断熱工法がおすすめです。
3:付加断熱(ダブル断熱)工法
付加断熱とは、充填断熱と外張り断熱の両方を組み合わせた工法です。建物の構造体内に断熱材を充填し、さらに外壁にも断熱材を貼り付け、高い断熱性能を実現します。
内外からの断熱により結露も発生しにくく、快適な室内環境を実現できるメリットもありますが、施工費用が高く工期が長いデメリットもあります。
費用や工期で心配な面もありますが、優れた断熱性能を求める人にはおすすめの工法です。
4:天井断熱工法
天井断熱とは、天井裏に断熱材を充填し、室内の熱の逃げを抑制する工法です。
天井から熱が逃げにくくなり冷暖房効率が向上するため、光熱費の節約や結露の防止が期待できます。室内の温度や湿度を保つため、快適な室内環境を維持することも可能です。
一方で、天井裏に断熱材を充填するため、小屋裏の収納スペースやロフトなどの空間利用が制限される場合があります。また屋根形状や天井構造によっては施工難易度が高く、コストもかかるでしょう。
比較的費用を抑えながら断熱性能をアップできる工法ですが、住宅の構造やライフスタイルに合わせて他の断熱性能との比較をおすすめします。
5:屋根断熱工法
屋根断熱とは、屋根裏や屋根自体に断熱材を施し、室内の熱の逃げを抑制する工法です。
屋根から熱が逃げにくくなり、冷暖房効率が大幅に向上するほか、屋根裏の温度上昇を抑え、夏場の室温上昇を抑制する効果が期待できます。また、冬は屋根裏からの熱の流出を防ぐため、室温低下を防ぎます。
一方で、屋根全体に断熱材を施すため施工費用が高く、工期が長いです。既存住宅へのリフォームをお考えなら、屋根の構造や状態によって施工が難しい場合もあるでしょう。
新築時に施工をする際にはおすすめの断熱工法ですが、既存住宅の場合は専門家への相談をおすすめします。
6:床断熱工法
床断熱とは、床下の空間に断熱材を充填し、室内の熱の逃げを抑制する工法です。
床下からの冷気を遮断すれば足元の冷えを防ぐことができ、暖房効率もアップします。さらに結露防止にも役立つのがポイントです。
一方で、床下の構造や形状によっては施工難易度が高く、費用がかかる場合があります。また、断熱材を充填しすぎると換気不足に陥るほか、シロアリ対策もより重要です。
寒さの厳しい北海道にぴったりな断熱工法ですが、構造に合わせて他の断熱方法と比較すると良いでしょう。
7:基礎断熱工法
基礎断熱とは、建物の基礎部分に断熱材を施す工法です。床下の温度を一定に保ち、建物全体の高断熱化に貢献します。
こちらも床下からの冷気を遮断し、暖房効率を大幅に向上させる効果が期待できるほか、床下の結露を防ぎカビやダニの発生を抑えるメリットがあります。床下を収納に使うこともできるでしょう。
一方で、基礎部分全体に断熱材を施すため費用がかかります。床下に対するシロアリ対策や湿気対策も必要となるでしょう。
新築時には施工しやすいですが、既存住宅へのリフォームなら専門家への相談をおすすめします。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
断熱材の主な種類
北海道で暖かい新築を建てるためには、断熱材の種類についても知っておくと便利です。ここで、断熱材の主な3つの種類についてご紹介します。
1:繊維系断熱材
繊維系断熱材は、細い繊維を絡み合わせて作られた断熱材です。
| 主な繊維系断熱材 | |
| グラスウール | ガラスを溶かして繊維状にしたもので、安価で入手しやすいのが特徴。 |
| ロックウール | 玄武岩を溶かして繊維状にしたもので、耐火性が高く、防火壁などに使用。 |
| セルロースファイバー | 新聞紙や古紙をリサイクルして作られたもので、環境負荷が低いのが特徴。 |
繊維系断熱材は空気を多く含む構造のため、高い断熱性能を発揮します。また比較的安価で入手できるため、コスパの良い断熱材と言えるでしょう。さらに、柔軟性が高くさまざまな形状の空間に対応できたり、音を吸収する効果が期待できたりと、メリットがたくさんあります。
一方で、一部の製品にはホルムアルデヒドなどの有害物質が含まれている可能性があります。湿気を吸収しやすい性質上、結露対策も必須です。
2:発泡プラスチック系断熱材
発泡プラスチック系断熱材は、プラスチックに気泡を無数に含ませたもので、軽量かつ高い断熱性能が特徴です。
| 主な発泡プラスチック系断熱材 | |
| 押出法ポリスチレンフォーム(XPS) | 高密度で強度が高く、湿気に強いのが特徴。地下や外壁などに使用。 |
| ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 軽量で加工しやすく、断熱材としては最も一般的な種類。 |
| 硬質ウレタンフォーム | 現場で発泡させて成形するため、隙間なく施工可能。断熱性能が高いものの、燃えやすいというデメリットあり。 |
発泡プラスチック系断熱材は気泡が熱を遮断する性質を持つため、高い断熱性能を発揮します。このほかにも、加工性が高く防水性・耐水性、気密性に優れているメリットがあり、施工性の良さから、住宅の断熱材として広く利用されています。
一方でコストが高く、火災時に有害ガスを発生させる可能性があるので注意が必要です。性質上熱に弱く、コストも高くなる傾向にあります。
断熱性能が高く扱いやすい反面、コストなども考慮しながら他の断熱材と比較検討することをおすすめします。
3:天然素材系断熱材
天然素材系断熱材は、自然由来の素材を主成分とした断熱材です。環境への負荷が少なく、人体への影響も少ない点が特徴です。
| 主な天然素材系断熱材 | |
| 木質繊維 | 木材を細かく砕いたもので、断熱性、調湿性、吸音性に優れている。 |
| 羊毛 | 羊の毛を加工したもので、高い断熱性と調湿性を持つ。 |
| コルク | コルク樫の樹皮から作られ、軽量で弾力性があり、断熱性、防音性にも優れている。 |
天然素材系断熱材は調湿性が高く、快適な室内環境を保ちます。加えて環境への負荷が少なく、有害な物質を含まないため、健康に優しい素材です。自然素材ならではの温かみを感じたい人にはうってつけでしょう。
一方で、人工的な断熱材に比べ高価であり、素材によっては施工に専門的な技術が必要になるケースがあります。肝心の断熱性能についても、人工的な断熱材に比べ劣る可能性があるでしょう。
このようなデメリットを理解しつつ、環境への配慮や健康面を重視する方にはおすすめの断熱材です。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
北海道で家を建てる際に断熱面で注意すべきこと
寒い北海道で暮らす人々にとって、家は快適な空間であるべきです。そのためにも、設計性能評価と建築性能評価の取得をおすすめします。
大切なのは、断熱性能が実際にどれくらいあるのかを示す「保証」と、設計通りの家が建つという「確約」です。残念ながら、仕様通りに建築されないケースや、施工ミスなどで断熱性能が期待通りでないケースも考えられます。こうした不安を解消するために、ぜひ設計性能評価書を求めましょう。
設計性能評価書とは、家を建てる前に、その家の断熱性能やその他の性能がどの程度あるのかを、専門の機関が詳しく調べて等級で表したものです。この評価書を契約書に一緒に付けたり、契約前に渡したりすると「建てる家が評価書に書いてある通りの性能を持っている」と建てる人に約束したことになります。
さらに、建築中の現場検査を受ければ、より確実な品質管理ができます。設計性能評価を取得したうえで、建築性能評価を受けておくと、設計書通りに建築されているか第三機関による現場検査が入るので安心です。
北海道では、設計性能評価を受けても建築性能評価を受けない住宅がたくさんあるため、必ず受けるようにしましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
家づくりのご相談は“ロゴスホーム”へ
北海道の寒い冬も、あたたかく過ごしたい。そんなお客様の声にお応えして、ロゴスホームは、高断熱・高気密の家づくりを行っています。快適な住まいを、無理のない価格で実現したいとお考えの方、ぜひ一度ご相談ください。冬もあたたかく、お財布にも優しい家づくりをご提案いたします。
失敗したくない方へ

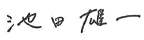

知りたかったたった
1つのこと

手に入れる方法
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
まとめ
北海道の寒さ対策は、断熱材の種類や厚み、施工方法など、さまざまな要素が関わってきます。また、住宅の断熱性能は快適な暮らしだけでなく、エネルギーの節約にもつながります。
これから家を建てる人はもちろん、リフォームをお考えの方も、断熱方法や断熱材の種類について知っておけば、この先きっと役立つはずです。
ロゴスホームでは、お客様一人ひとりのご要望に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。