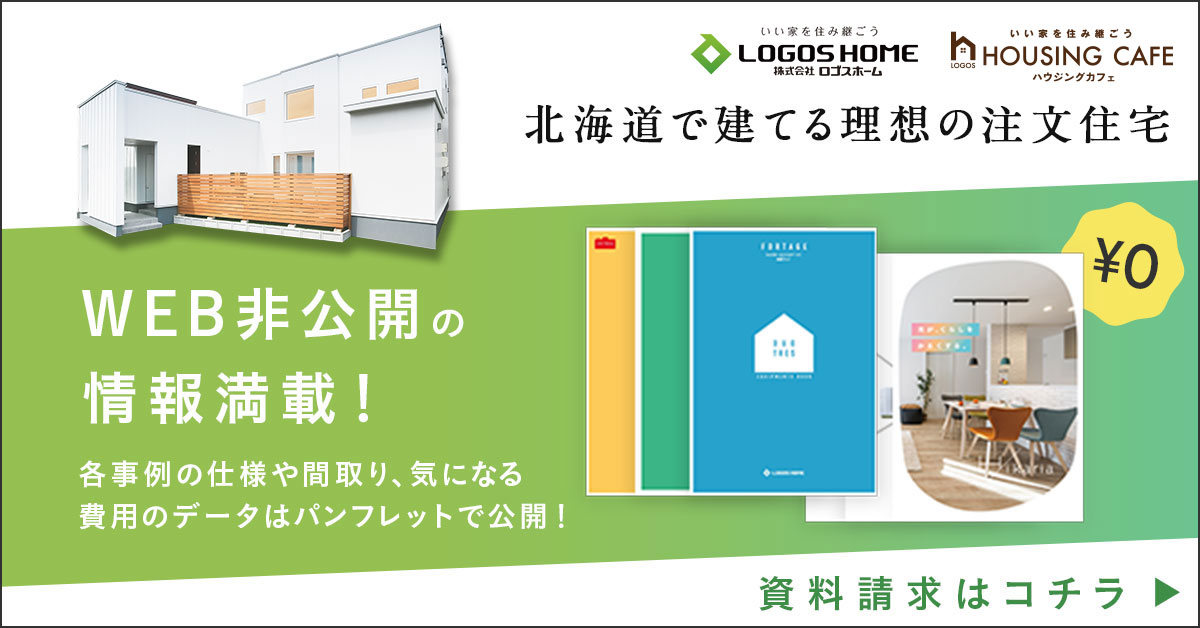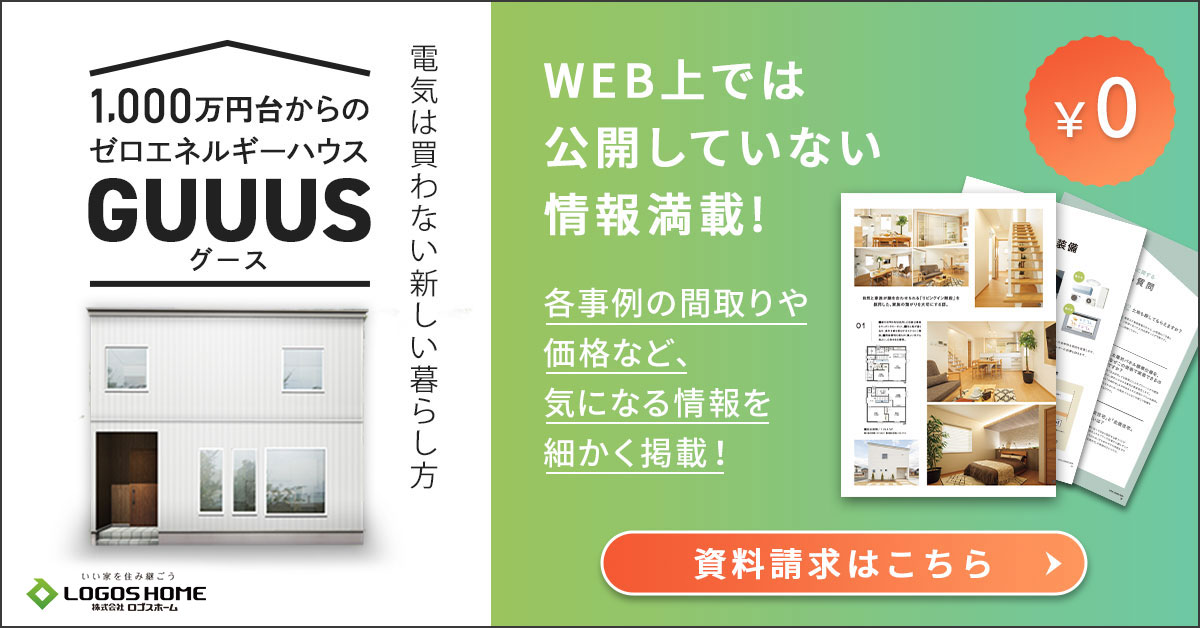この記事の目次
注文住宅を建てる際にかかる費用を抑えるには、その内訳を知ることが重要です。
この記事では、注文住宅の建築に必要な主な費用の内訳と、予算を効率的に管理する方法について解説します。
注文住宅の費用内訳とは?
1:土地に関する費用
土地を購入する際は、土地代に加えてさまざまな諸費用がかかります。
土地に関する費用として、代表的な項目について次の表にまとめました。
表の項目以外にも、申し込み時の申込金、契約時の手付金、土地家屋調査士に依頼するときの測量費用などがかかる事例もあります。
| 費用の種類 | 概要 | 支払いのタイミング |
| 仲介手数料 |
・不動産会社の仲介で土地を購入したときに支払う手数料(売主から直接購入した場合はかからない) |
売買契約時と引き渡し時の合計2回に分けて支払う(不動産によって支払いの時期が異なるケースもある) |
| 不動産売買契約書の収入印紙代 |
・契約書の作成時に国に対して納める税金 |
売買契約時 |
| 登録免許税・所有権移転登記などの登記費用 |
・土地の所有権が移動したことを申請・登記するときにかかるのが所有権移転登記費用 |
引き渡し時 |
| 不動産所得税 |
・不動産を取得した人に対して課税される税金 |
不動産を取得してから半年〜1年ほど |
| 固定資産税・都市計画税 |
・土地の売買で所有権を移転するときに、1年の中で売主と買主それぞれが所有している時期があるため、固定資産税と都市計画税を日割り精算する商業取引の習慣がある(地方税法上で規定されているものではない) |
引き渡し時(日割りで買主から売主へ負担金を渡して精算する) |
| 住宅ローン手数料や収入印紙税など |
・先に土地だけを購入するときに「つなぎ融資」と呼ばれる一時的なローンを利用するときにかかる費用 |
住宅ローン実行日 |
2:建物本体の工事に関する費用
建物本体にかかる費用は、大きく分けると「建物本体工事費用」「別途付帯工事費用」「諸費用」の3つに分類されます。
建物本体の工事に関する費用それぞれの割合や支払いのタイミングを次の表にまとめました。
| 費用の種類 | 総費用に対する割合 | 支払いのタイミング |
| 建物本体工事費用 |
約70〜80% |
約時、着工時、上棟時、引き渡し時の合計4回に分けて支払う |
| 別途付帯工事費用 |
約15〜20% |
|
| 諸費用 |
約5〜10% |
手続きによって異なる |
住宅ローンを取り扱う住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査結果」によると、注文住宅にかかる総費用の全国平均額は3,863万円でした。
全国平均額を3,800万円とすると、2,660〜3,040万円が建物本体工事費用で、570〜760万円が別途付帯工事費用、190〜380万円が諸費用になる計算で内訳の目安になります。
支払いのタイミングはハウスメーカーによって異なり、建物完成後の引き渡しまでに分割して支払うのが一般的です。
支払いの分割は、契約時に手付金として10%前後、着工時に着工金として30%前後、上棟時に中間金として30%前後、完成後の引き渡し時に30%前後といった流れで支払われます。
住宅完成前の工事費用の支払いには住宅ローンが適用されないため「つなぎ融資」を利用して工事費用に充てる方が多いです。
参照:
住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査結果」PDF10ページ「所要資金(融資区分別・全国)」の注文住宅より
本体工事費用の内訳詳細
建物の本体工事にはどのような費用が含まれているのか、木造住宅を事例に、具体的な工事の内容を表にしました。
| 費用の種類 | 工事の内容 |
| 仮説工事 | ・建設工事中の一時的な設備の工事・建物内部や外部の足場や敷地の囲い、工事用の電力、仮設トイレ、駐車場料金など |
| 基礎工事 | ・建物と地面を繋いで構造を支える「基礎」をつくるための工事・地盤が弱い場合は地盤改良が行われ、地盤改良費用が発生する |
| 木工事 | ・木材を加工・組み立て・取り付けする工事で、大工が中心となって行う作業・木造住宅の建築において最も重要な工事であり、工事費の中で大きな割合を占める |
| 外装工事 | ・屋根や雨樋、屋上、外壁、防水、塗装工事など建物の外壁に関する工事が含まれる |
| 内装工事 | ・建物内部の壁、床、天井の表面を仕上げる工事・木製建具の設置、ボード・クロス貼り、左官、床の仕上げなど |
| 設備工事 | ・エアコンや床暖房、システムバス、キッチンなどの設備を設置する工事・設備ごとのグレードやオプションによって費用が異なる |
| 設計費用 | ・建物の設計を建築士に依頼するとかかる費用・工事費用全体の10〜15% |
注文住宅を建てるには、上記の通り、さまざまな工事が必要になります。見積もりをチェックするときの参考にしましょう。
3:付帯工事費(別途工事費)
別途付帯工事費用とは、建物以外の工事を行う際にかかる費用です。
付帯工事に含まれる主な工事と工事内容を次の表で紹介します。
| 費用の種類 | 工事の内容 |
| 屋外設備工事 | 電気・ガス・水道など公共インフラを敷地内に引き込む工事 |
| 外構エクステリア工事 | 住宅敷地内の外側はエクステリアと呼ばれ、外構エクステリア工事とは屋外空間の工事を指す門扉やフェンス、玄関アプローチ、植栽、カーポート、ウッドデッキ、庭など外構の工事を行う |
| 空調設備工事 | エアコンや室外機の設置工事など室内の空調に関わる工事 |
| カーテン工事 | カーテンレール・カーテンやブラインドを取り付ける工事 |
| 照明器具工事 | 照明器具を取り付けたり、照明システムを設計したりする工事(照明器具は本体工事に含まれるものもある) |
| 解体工事 | 既存の建物を解体して敷地に何もない状態に戻す工事 |
| 地盤改良工事 | 地盤調査の結果、地盤改良が必要になった場合に地盤の強度を向上させる工事 |
| 造成工事 | 住宅用ではなかった土地を、住宅地として利用するために行う工事傾斜のある土地を平坦にしたり土地を区画して形を変えたりする工事を行う |
他にも、テレビを見るときに必要な設備を設置する「テレビ工事」や、建物に水や湯を供給・排水する設備を設置する「給排水工事」などがあります。
建築会社によっては本体工事費用に含まれる工事もあるので、ハウスメーカーに問い合わせて内訳を確認しておきましょう。
4:諸費用
諸費用とは、土地や建物の購入価格や建築費用以外にかかる費用や手数料の総称です。
建物に関する諸費用の目安は、建築費用全体の5〜10%前後とされています。
どんな費用が諸費用に含まれているのか、種類別に費用の内容と支払いのタイミングを見ていきましょう。
| 費用の種類 | 概要 | 支払いのタイミング |
| 工事請負契約書の収入印紙代 | ・工事請負契約書とは、工事発注者と受注者が工事の完成や報酬の支払いを約束するもの・契約書の作成に対して課される税金が収入印紙代・契約書に記されている金額に応じて納める収入印紙代が異なる | 売買契約の締結時 |
| 所有権保存登記費用・登録免許税 | ・新築した建物が自分の所有物であると証明するための手続きが所有権保存登記・登記するには登録免許税の支払いが必要 | 引き渡し時 |
| 建物表題登記の費用 | ・建物表題登記とは、建物の所在や地番、構造、床面積などの物理的状況を登記簿に記載する手続き・建物表題登記の手続きでは登録免除税は不要・専門の土地家屋調査士に依頼する場合は依頼費用がかかる | 引き渡し時 |
| 火災保険料・地震保険料・団体信用生命保険料 | ・住宅ローンを組む際は火災保険への加入が原則・地震保険は単独で加入ができないので火災保険とセット加入が前提・団体信用生命保険料とは、ローンの債務者に何かあったときに支払い義務をなくせる制度 | 引き渡し時 |
| 不動産取得税 | ・家屋の建築などで不動産を取得した人に対して課される税金・土地の不動産取得税と同様、取得したときに一度だけ支払う | 不動産を取得してから半年〜1年ほど |
| 住宅ローン関連の費用 | ・お金の貸し借りに関する詳細が記載された金銭消費貸借契約書の収入印紙代・融資にかかる手数料・万が一返済不能となったときに保証会社が金融機関へ残金を支払うローン保証料、不動産を売って回収できる抵当権設定登記の費用など | 住宅ローン契約の締結時 |
各社の見積もりを比較するときは、諸費用を含めるといくらになるのかを確認し、予算に収まるように資金計画を立てましょう。
5:その他費用
注文住宅を建てる際、その他にかかる費用と内容、一般的な相場を表にまとめました。
| 費用の種類 | 内容 | 一般的な相場 |
| 地鎮祭 | 地鎮祭とは、着工前に土地の地主神を祀り、工事の安全や土地・建物の末永い安全を祈願する儀式 | 10〜15万円前後 |
| 上棟式 | 上棟式とは、建物の基本構造が完成し、棟木を上げるときに執り行われる儀式 | 5〜8万円前後 |
| 引越し費用 | 引越し業者に払う費用(アパートから引越すなら退去費用なども必要) | 荷物量や移動距離、時期によって異なる |
| 家具・家電購入費用 | テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・照明器具・シェルフ・キャビネット・ソファ・ダイニングテーブル・食器棚など | 100万円前後 |
| 挨拶回りの粗品購入費用 | 新居に引越した後ご近所に挨拶回りをするときに持参する粗品 | 粗品1つあたり500〜1,000円前後 |
これらの費用を含め、自分の予算に合った購入費用で、ゆとりのある資金計画を立てましょう。
\あわせて読みたい!/
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
注文住宅の費用相場とシミュレーション
注文住宅の一般的な費用相場はどのくらいなのか、全国平均を参考にしてシミュレーションしていきます。
総額はどの程度の費用か、土地代は総額の何%程度か、土地購入込みの注文住宅シミュレーションと、土地購入なしの注文住宅シミュレーションから費用相場を理解しましょう。
土地購入込みの注文住宅の費用相場とシミュレーション
土地購入を含んだ注文住宅の全国平均購入資金総額は、約5,112万円であり、自己資金比率は約23.5%です。
土地購入なしの注文住宅の費用相場とシミュレーション
一方、土地購入を除いた注文住宅の全国平均の購入費用は、約3,459万円で、自己資金比率は約28.1%でした。
さらに、注文住宅の費用は地域によっても大きく異なります。
都市部では土地の価格が高騰する傾向にあり、そのため、同じ広さや仕様の家を建てる場合でも、都市部では地方に比べて総費用が高くなることが一般的です。
例えば、東京都心や大阪などの主要都市では、土地の価格が地方都市や郊外に比べて高いため、全体の建築費用もそれに比例して増加します。
一方で、地方では土地価格が比較的安定しているため、同じ品質や仕様の家を建てた場合、都市部に比べて全体の費用が抑えられる傾向にあります。
また、地域によっては、住宅建設を促進するための補助金や税制優遇措置が提供されることもあり、さらに低コストでの建築を可能にしています。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
注文住宅の予算別の特徴と費用計画の立て方
注文住宅はかけられる予算によって求められるクオリティが異なってきます。
予算別の注文住宅の特徴は下記です。
| 注文住宅の予算別の特徴 ・1,000万円代:コストを抑えるために外観や間取りがシンプルになり、建物形状は正方形や長方形などの四角形が多くなります。コストダウンを測りやすいように1階と2階が同じ面積である総2階建ての建物で、間取りや設備はいくつかのプランから選ぶようになるでしょう。 ・2,000万円代:ある程度は間取りや外観、内装にこだわりながら設計できますが、優先順位をつけて費用をかける部分を決めないと、予算オーバーになる可能性もあります。内装や外装よりも住宅設備にお金をかけるなど、メリハリが必要です。 ・3,000万円代:工法や省エネルギー、耐震性など住宅性能にこだわりながら、価格帯が高いハウスメーカーから選べるでしょう。吹き抜けがあるような開放感のあるリビングや、設備や外壁、内装もグレードを上げやすくなります。 ・4,000万円代:家族一人ひとりの居住面積を確保しながら、中央部に中庭を配置するような設計も考えられます。木造よりも単価が高く、耐震性・耐久性のある鉄骨造も検討できて、壁や柱が少ない広々とした間取りも実現可能です。 |
注文住宅の費用計画を建てるには、上記の予算別の特徴と相場を理解しつつ、次のようなステップを踏みましょう。
・用意できる自己資金(頭金)を用意する
・住宅ローンの借り入れ金額を決める
・住宅ローンの種類を選ぶ
注文住宅の費用には、土地の購入代、建築費用、諸費用などが含まれます。また、住宅ローンの返済額や金利タイプ、返済期間なども考慮しましょう。
\あわせて読みたい!/
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
注文住宅の費用を支払うタイミングはいつ?
注文住宅の一般的な費用相場はどのくらいなのか、全国平均を参考にしてシミュレーションしていきます。
総額はどの程度の費用か、土地代は総額の何%程度か、土地購入込みの注文住宅シミュレーションと、土地購入なしの注文住宅シミュレーションから費用相場を理解しましょう。
1:土地代金を支払うタイミング
土地の購入代金は、基本的に「売買契約時」と「引き渡し時」の2回のタイミングで支払います。
売買契約書を結ぶ時にまず手付金として5~10%を、残りの金額はローンの審査が通った後に、土地売主に対して払うことが多いです。
2:建物代金を支払うタイミング
注文住宅における建物代金の支払いタイミングは、主に「着工時」「上棟時」「引き渡し前」の3つのタイミングに分けられます。
- 着工時:建築が開始する際に必要となる「着工金」として、工事費用の約30%が支払われます。この際、地鎮祭の費用なども含まれる可能性があります。
- 上棟時:建物の骨組みが完成した「上棟」のタイミングで、再び工事費用の約40%を「中間金」として支払います。この時期には上棟式の費用も発生することがあります。
- 引き渡し前:建築がほぼ完了し、引き渡しを控えている段階では、建築費の残金を支払います。建物の登記費用などもこのタイミングで支払うことが一般的です。
以上が一般的な建物代金の支払いタイミングですが、具体的なスケジュールや金額は契約内容や建築会社の方針によって異なる場合があります。
そのため、詳細は各建築会社との契約に基づき確認することが重要です。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
注文住宅の費用を抑えるポイントはある?
「注文住宅を建てたいけれど予算をオーバーするかもしれない」と踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
注文住宅で費用を抑えるには、妥協できるところを探して節約する必要があります。
ここでは、注文住宅で節約するには、どのようなポイントを見直せば良いのか、節約ポイントについて具体例とともに解説していきます。
土地代にかけられる予算を減らす
土地の予算を減らすには、駅から離れた土地や、メインとしている駅の土地から隣の駅の土地を検討してみましょう。
また、日当たりの問題で避けられやすい北向きの土地や、三角形や台形など少し変わった形の土地も割安になります。
このような土地は、理想とする間取りを叶えられなかったり、暮らしにくかったりするデメリットもありますが、土地の特徴に合わせて設計すれば快適な家づくりも実現可能です。
土地探しはハウスメーカー選びと並行して進めて、土地と建物にかける予算配分を調整しましょう。
建物の床面積を小さくする
注文住宅の建築費用は「坪単価×床面積」が目安であり、床面積を減らすだけでコストダウンが期待できます。
| 【床面積を減らした際のコストダウン例】 坪単価70万円・床面積40坪の家を建築する場合70(万円)×40(坪)=2800(万円) ▼床面積5坪減らしたケース70(万円)×35(坪)=2450(万円)▶︎350万円の費用削減 |
しかし、ハウスメーカーによっては床面積の出し方が異なるので注意が必要です。
床面積を小さくするときは、以下のどちらの方法で面積を出しているのかをハウスメーカーに確認しましょう。
・施工床面積:ベランダ・玄関ポーチ・地下室など施工する全ての床面積を含む
・延床面積:ベランダ・玄関ポーチ・地下室など含まない床面積
建築費用を抑えるようなプランや設備を選ぶ
注文住宅は凹凸が多いほど外壁量や作業量が多くなり、その分費用もかかるので、凝ったデザインの家よりも、外壁の凹凸が無いシンプルな形状の方が建築費用を抑えられます。
また、窓の面積を減らしたり、浴室やキッチンなどの設備のグレードを下げたり、低コストな仕上げ材を選んだりするだけでもコストダウンできます。
ただし、建築費用を節約できたとしても、メンテナンス費用が割高で、建物自体の質が落ちるような建築プランは避けましょう。
建築費用の見積書はハウスメーカーによって異なります。付帯設備工事が含まれているのかなど、ハウスメーカーごとの提案内容をそれぞれ比較検討しましょう。
セミオーダーできる注文住宅を選ぶ
注文住宅におけるセミオーダーとは、家の仕様や間取りの一部を自分で決められる住宅を指します。
ハウスメーカーが用意している間取りのパターンから選ぶので制約はありますが、完全自由設計よりも費用を抑えられ、事前にイメージしやすいためスムーズに決められます。
セミオーダーで採用されている仕様や間取りは人気のパターンであり、失敗しにくいといったメリットもあります。
賃貸併用住宅を考える
賃貸併用住宅とは、自宅と賃貸住宅を1棟の建物にまとめた住宅です。
自宅と賃貸が一体となった賃貸併用住宅を建てると、賃貸の家賃収入を住宅ローンの返済に充てられるなどの利点があります。
特に、駅から近い土地など賃貸の需要が多いエリアに注文住宅を建てる方や、将来的に親や子どもとの二世帯住宅を考える方にもおすすめです。
税金制度や補助金制度を利用する
家を購入した際に、条件に当てはまれば固定資産税を軽減できる優遇制度や、補助金・給付金など負担を削減する軽減制度を利用できます。
自治体によっては、省エネルギーや耐震性能、断熱性能に優れた住宅の建設に補助金が支給されます。
お住まいになる予定の自治体の支援や支援に関する条件を調べ、利用できる制度は活用しましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
家づくりのご相談は”ロゴスホーム”へ
ロゴスホームは「高品質」「高性能」「適正価格」を約束してお客様に寄り添い、ご希望を叶えながら建築してきました。
北海道の住宅着工件数ではNo.1を獲得しており、厳しい寒暖差にも耐えられる快適な家づくりが可能です。建築後20年の長期保証制度に加え、建築後10年間で5回の定期点検を行っていて、充実したアフターフォローをご用意しています。
また、ロゴスホームには完全自由設計のプランや予算1,000万円の費用にこだわったプランがあるため、理想の家づくりができるプランが見つかるでしょう。
お客様のライフスタイルに合った住まいのご提案から、土地探し、設計、施工まで経験豊富な各分野の専門スタッフがトータルサポートするので、ご希望の資金計画に合わせることも可能です。
建築費用を抑えつつ理想の注文住宅を建てたいと考える方は、ぜひロゴスホームまでお気軽にご相談ください。
失敗したくない方へ

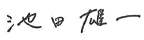

知りたかったたった
1つのこと

手に入れる方法
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
まとめ
注文住宅を建てる際、その費用は土地選びから建築コスト、諸費用まで多岐にわたります。
総費用を抑えるためには、土地の価格、建築方法、資材選択の工夫が必要です。
また、賃貸併用住宅の選択や税金控除、補助金制度の活用も有効です。
最終的にあなたの理想の家を実現するためには、コストのバランスを考慮し、専門家のアドバイスを活かすことが重要です。